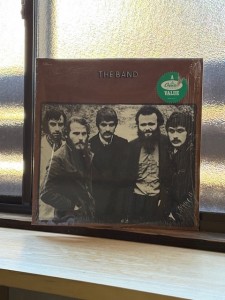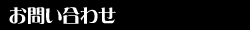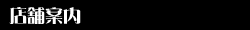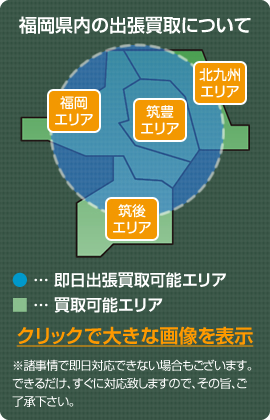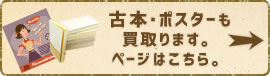現実に起きたレコードの都市伝説
先日、長崎県から福岡市西区の当店まで、
1970年代ロック・レコードをメインにした持ち込み買取がありました。
当店はなぜか長崎からの買取が多い。
距離のわりに高速インターから近いのも理由でしょうか。
ありがたいことです。
その中に、ザ・バンドのセカンド・アルバムの
1980年代前後の再発レコードが入っていました。
これがまた “いかにも再発” という感じで、
溝が薄くて盤がペラペラ。
当店のプレーヤーは針圧が軽く調整できないので、
ザ・バンドのあのリズムの塊のようなサウンドに
果たして耐えられるのか?
と不安になりながら再生チェック。
案の定です。
リズムの権現みたいな「クリプル・クリーク」で、
傷もないのに音が飛ぶ。
ザ・バンドの“音がぶつかってくるような力”に、
この薄い再発盤が完全に負けてしまった形です。
これは都市伝説のように聞こえますが、現実、傷がないのに音が飛んだのは事実で、その後コインを乗せることで針圧を重くし、無事再生できました。
今回のブログは、
この「ザ・バンドの恐るべき音の塊」 がテーマです。
あのレコードは「怪物」だ
やっぱりあの音楽は「生き物」であり「怪物」だ。
ロックでもフォークでもブルースでもない。
あれは5人の呼吸と気配がそのまま音になっている“生命体の音楽”。
よく「ザ・バンドはアンサンブルが凄い」と言われる。
そんな薄い言葉じゃ説明できない。
彼らの音はもっと“野生的”で、“詳細すぎる自由”が詰まってる。
即興じゃないのに、ジャズよりフリー
普通なら
「即興=自由」
「ロック=構造」
というイメージだが、彼らは違う。
決めてあるはずのフレーズが、まるで勝手に動き出しているように聴こえる。
• コーラスが“入ろうと思った瞬間”にフワっと入る
• 終わり方が誰にも読めない
• 楽器同士が呼吸で方向を変える
• 一人の感情が揺れると全員が連動する
これ、ジャズの即興より自由。
なぜか?
5人全員の“気配”が同期しているから。
技術じゃなく、意識でもない。
まるで体温や心拍が同じになってるような動き。
「せーのでやるロック」は恥ずかしくなる
ザ・バンドを聴くと分かる。
普通のロックバンドが“せーので合わせる”のは、
あれだけの自由を聴いた後だと、ものすごく窮屈に感じる。
• 決めてガッとやる
• クリックで合わせる
• 同じリフを揃える
もちろんこれが悪いわけじゃない。
ただ、ザ・バンドの演奏が異常すぎるだけ。
勝手に動く音が、自然にひとつの方向へまとまっていく。
これを聴いたら、
「せーので合わせるロック」に
少し恥ずかしさすら感じてしまう。
“魔法”を持つバンドはほとんどいない
音楽史を見ても、
このレベルの“魔法”を持つバンドは本当に少ない。
自分の感覚で言うなら、
• ビートルズ初期(ハードデイズ辺りまで)
• ザ・バンド
• ロバート・ジョンソン
このあたりが同じ種類の“生きている音楽”。
「技術」でも「アレンジ」でもなく、
存在そのものが鳴っている音楽。
これは作ろうとしてできるものじゃない。
ザ・バンドのセカンドは“生命体の記録”
特にセカンドは完成度が異常だ。
曲そのものは静かでも、
内部で大きなエネルギーが蠢いている。
演奏もコーラスも、
まるで「気配→音」になっている。
意図ではなく、自然現象。
最後に
ザ・バンドを語るときに、
「上手い」「高度」「緻密」
そんな言葉は全部当たり前。
本当の凄さはそこじゃない。
即興じゃないのに、即興以上の自由がある。
5人が生命体のように動く。
音楽が勝手に流れ始める。
これがザ・バンドの魔法。
セカンドは“録音された生き物”だと思って聴くと、
全く違う音が聞こえてくる。
カントリー・バンド否ザ・バンド
直前にハンク・ウィリアムスを聴いていた。
ザ・バンドもカントリー風のバンドに聞こえる。
でもすぐに「いや違う」と分かる。
ハンクは天才だ。
でもザ・バンドのセカンドに触れると、もっと大きいものに気づく。
ハンクを含む、アメリカ音楽の多くの天才たちが作った“根”に、
五人の怪物が超一流の味付けをしてしまった結果が、この音だ。
ルーツ音楽の素材は素朴なのに、
出来上がった音は異常に深い。
この「天才の素材 × 五人の怪物」の構造はザ・バンドだけ。
福岡のレコード・CD買取致します
国内盤、輸入盤問わず、ジャズ、ロック、ソウル、ブルース、R&B、ワールド・ミュージック、日本の音楽などのレコード、CD、買取、出張買取、店頭(持ち込み買取)、宅配買取致します。
福岡県福岡市の中古レコード屋・中古CD屋アッサンブラージュ。